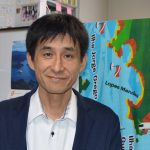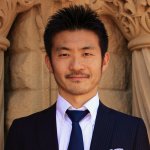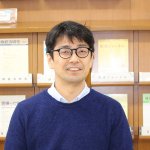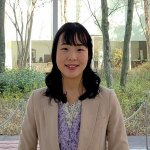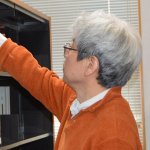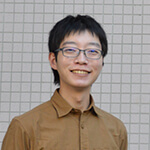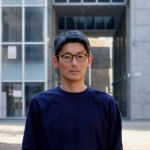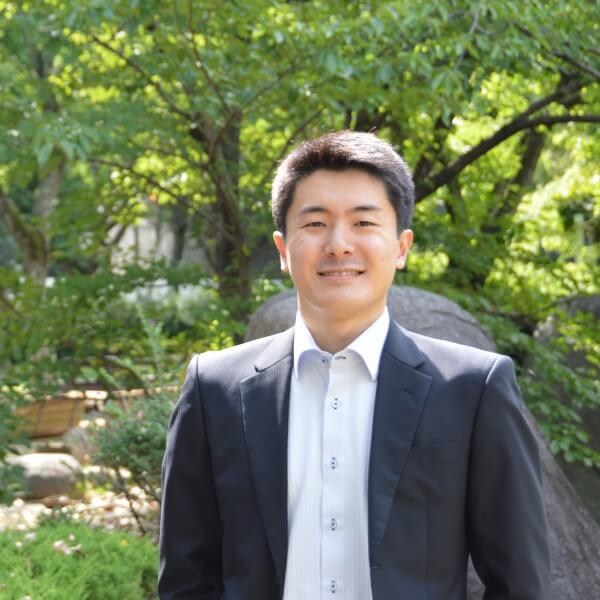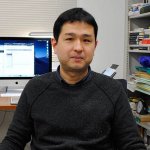川窪 悦章
専門分野
国際経済学、組織の経済学、公共経済学
研究テーマ
サプライチェーンの脆弱性とレジリエンス、企業の生産性
研究紹介
近年、Brexitや米中貿易摩擦、コロナ禍、ウクライナ侵攻、度重なる自然災害など、世界のサプライチェーンは大きな混乱に陥っている。スーパーにおける食料品価格の高騰や自動車産業における工場の操業停止など、国際経済のあらゆる側面で混乱が生じており、日本経済もその例外ではない。
1990年以降、企業はグローバリゼーションの進展に伴い、生産拠点をコストの低い地域に配置し、部品や原材料を安価に調達することで、生産性を高めようと努めてきた。しかしながら、2020年頃からは一転して、企業はサプライチェーンのリスクと不確実性に晒され、生産・調達における大きな転換を迫られている。このようなサプライチェーン上のリスクは、気候変動や地政学的な理由から、今後より頻繁に発生することが予想され、今後取るべき政策について詳細な分析が急務となっている。
サプライチェーンにおいてショックが生じた際、「企業はどのようにすれば被害を緩和できるのか」、そして「どうすればショック自体を避けられるのか」を分析するために、近年は民間企業のデータを用いた研究を行ってきている。私は、2011年の東日本大震災後に注目した研究で、企業がどのようにサプライチェーンを再構築したのか、またそれにより負の影響をどこまで免れることができたのかを分析した。被災地外に位置する企業を①サプライヤーが被災した企業と②そうでない企業とに分けたうえで両者を比較したところ、前者①の企業は11年以降、速やかに被災地外のサプライヤーを増やすことで、震災の影響を免れようとしたことが明らかになった。ただし、震災前の時点で被災地内のサプライヤーとの取引年数が長かった企業に関しては、迅速に代替的なサプライヤーを探すことができず、売上に負の影響が出ていたこともわかった。つまり、震災が起きた段階で、特殊な部品の仕入れなどを行っており、被災地に結びつきの強いサプライヤーを有していたような企業は、ほかの企業からの仕入れに移行することが難しく、生産活動が阻害されてしまったのだ。この分析結果からは、サプライチェーンのレジリエンスには、状況に応じた迅速な取引ネットワークの組み替えが肝要であることが示唆されており、迅速な組み換えを促進するための政策的な議論が期待される。
また、最近の研究では、民間企業の秘匿データや政府の業務データを用いることで、ショックに対する企業の行動やサプライチェーンの組替えに関する分析を行っている。
川窪 悦章
KAWAKUBO, Takafumi
講師:Lecturer
学位:博士(経済)(LSE, UK)
tkawakubo.osipp@osaka-u.ac.jp
OSIPP Faculty