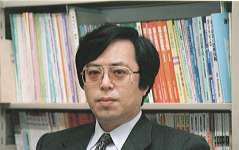亡国の土建国家から脱却を
跡田 直澄(公共経済学、教授)
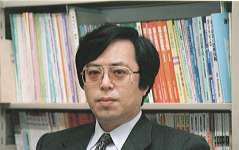
- <公共事業が生み出した土建国家>
国と地方を合わせた近年の公共事業額は50兆円弱。バブル期には国と地方の歳出純計額に占める同様な公共事業の割合は25%前後であったが、バブル崩壊後には30%前後にまで跳ね上がっている。
これだけの規模の景気対策を行ってきたにもかかわらず、その効果は不況の深刻化に歯止めをかける程度のものにすぎなかった。しかも、悲劇的なことに、その実施の最も顕著な効果が建設業の就業者数の増大でしかなかった。
建設業を肥大化させただけの土木事業偏重型景気対策。これが多くの利権と政界・官界・財界の間に癒着を生み出し、わが国を異常なまでの土建国家に変えてしまった。
- <行政の限界>
こうした実態を背景として、景気対策としての公共事業への批判が高まり、ケインズ政策からの撤退までが表明された。しかし、近年の補正段階での景気対策では、中小事業者への小規模事業の多量発注や公共事業用地先行取得という形で予算が消化された。これでは通常の乗数効果が発揮されるはずがない。
非効率な公共事業を景気対策として行ったことが乗数効果を低下させた。この点が議論されないまま、公共事業の景気浮揚機能の低下だけが必要以上に喧伝されている。問題の本質は、景気対策となりうる公共事業を企画する能力を行政が失っていることにある。この行政の限界を打破するには、事業内容の決定段階にコンペ方式の導入を検討すべきであろう。
- <亡国の公共事業>
景気刺激効果の減退とともに、近年の公共事業は生産力の向上にも寄与していない。公債発行により形成された公的資産が経済成長を実現しないと、税の増収による借金返済が不可能となり、負債を累積させることになる。92年頃からの公債残高の急増は、まさにこの状況を反映している。しかも、そのような資産が以前から累積されているならば、保有資産の市場価値は帳簿上での評価額よりかなり低いはずである。
国鉄清算事業団、国有林野事業などについては、すでに資金回収など望むべきもないほど資産内容が悪いことは判明している。わが国全体でみた時に、負債に見合うだけの資産があるのか、あるいは投下資金を回収できるだけの優良資産を保有しているといえるのであろうか。景気対策としてだけでなく生産力向上にも役に立たず、赤字を累積させているだけであるならば、亡国の公共事業といわざるを得ない。
- <事業評価の必要性>
来年度当初予算案では、さすがに公共事業も7.8%削減されることになっているが、これにしても各種の社会資本整備計画の延長により単年度支出を抑制した結果の数値にすぎない。五か年計画が七か年計画に変更されただけで、すでに策定された整備計画の公共事業総額は内容的には何等見直されず、結果的には完全実施される。これでは単に単年度の歳出を削減したにすぎず、真の財政構造改革にはならない。
財政システムを発展途上型から成熟社会型に変革しなければ、真の財政構造改革は達成できない。従来の整備計画にもとづく公共事業のように欠乏を補おうとする形のものから、国民が求めるもののうち社会的にみて有用なものを形成していく形に変えていくことが今求められているのである。そのためには、社会資本整備が持つ社会経済的効果の事前的な評価を通じて、なにが必要かを明らかにすること、さらには事後的な評価を通じてその事業の必要性を再チェックすることが重要なのである。
単なる不足を補う公共事業の時代は終わった。便益性・有効性の評価にもとづいた真に必要な公共事業の実施。これなくして土建国家からの脱却はありえない。

シンクタンク探訪
大和銀総合研究所
「関西、アジアに軸足を置いた地域密着型のシンクタンク」(伊勢戸義彦・企画渉外本部長)として、特徴性を出している。大和銀行を母体として1987年に設立。研究員は約110人で、主として東京本社が全国的なマクロ経済、大阪本社が関西圏の地域経済を担当。規模としては中堅だが、大和銀行譲りの「関西に根を生やした」研究活動で成果をあげている。
中でも注目されるセクションが「近畿経済研究部」。同部では毎年近畿2府5県(福井も含む)における近畿経済見通しを発表。この見通しは他社には例のないもので、信頼度も高い。それによると今年の近畿圏の見通しは、成長率は国レベルより0.1%低く1.1%。昨年よりはよくなり、明石海峡大橋の開通という好材料もあるが、産業構造として中小企業が多く、アジアの経済混乱の影響などもあり、景気はさほど改善しないという。
また、同部ではこれまで、関西国際空港の経済効果、阪神・淡路大震災の復興需要など地域性がありタイムリーな自主研究も実施。昨年は、今年4月に開通する明石海峡大橋の経済効果を分析し、他社に先駆けて発表した。それによると、開通により1507億円の経済効果が予想され、近畿の成長率は0.18%押し上げられる見込み、とされている。
海外拠点はロンドンと香港に置き、特に成長著しいアジア・オセアニア地域を重視している。「経済調査」「アジア・オセアニア情報」「ダイワアーク」などを発行、研究環境は各人の持ち味を生かし、自主研究も行えるよう配慮されているという。