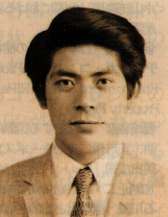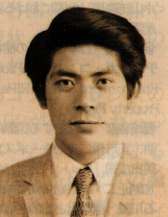活動報告(1996年度・その2)
論文発表
- 「Nuclear Disarmament and Non-Proliferation: Japanese and Canadian
Perspectives」『Osaka University Law Review』No. 44 黒澤満
教授
- 「ドイツ家庭法立法の現状と展望(2)」『阪大法学』46巻6号
- 「子どもの権利条約と家庭法改正」『子どもの権利条約シンポジウム報告書』
(大阪弁護士 会少年問題対策特別委員会) 以上 床谷文雄助教授
- 「クライシス管理の経済政策へ」『郵政研究所月報』 96年8月号 No.
95
- 「『神戸進出が成功の鍵』となる拠点づくりを―神戸起業ゾーンがテイクオフ」『産業復興』(阪神・淡路産業復興機構)
以上 林敏彦教授
- 「Unit Roots and Cointegration Analysis: The Impact on Empirical
Analysis in Economics」 『Japanese Economic Review』1997,Vol. 48,
No.1 Colin McKenzie助教授
- 「『女性の人権』の視点と刑事司法」 『中山研一先生古希祝賀論文集』(第4
巻 「刑法の諸相」) 森本益之教授
- 「非営利革命とNPOの制度改革」『地域福祉研究』No.24
- 「政府のリストラク チャリング」『21世紀の日本経済と企業経営』(大阪大学)
- 「ノンプロフィット ・エコノミー (1)非営利の世界への招待(2)非営利セクターの経済構造
(3)寄付 の経済理論 (4)寄付とボランティア (5)企業フィランソロピー (6)財団の経済分析
(7)非営利組織の行動モデル (8)非営利病院の経済行動 (9)NPOとしての私立学校(10)寄付税制の経済効果
(11)寄付税制の実証分析 (12)NPOの制度改革」『 経済セミナー』96年4月〜97年4月号(日本評論社)
以上 山内直人助教授
著作
- 『日本会社史研究総覧』(第6章:綿紡績業) 経営史学会編 文眞堂
- 『近代日本における企業家の諸系譜』(第2章:堺段通業界の組織者) 竹内常善、阿部武司、沢井実編 大阪大学出版会 以上 阿部武司教授
- 『論考憲法学氈A』(統治機構、人権論) 伊藤公一、榎原猛、佐伯宣親、土居
靖美編 嵯峨野書院 伊藤公一教授
- 『軍縮問題入門』(編著「冷戦後の軍縮:現状と展望」「戦略兵器の制限と削減」「核兵器の不拡散」) 東信堂
黒澤満教授
- 『What's 経済学』(共著) 有斐閣
- 『ネットワーク未来』(共著) 日本評論社 以上 辻正次教授
- 『新編 女性のための法学』(「子の出生と親子関係」) 中川淳編 世界思想社
床谷文雄助教授
- 『現代国際取引法講義』(「国際金融」) 松岡博編 法律文化社 野村美明
教授
- 『ハート&マインド経済学入門』 有斐閣 林敏彦教授
- 『日本の資本市場』(第5章:日本のコマーシャルペーパー市場) 橘木俊詔
、筒井義郎編 日本評論社 Colin McKenzie助教授
- 『新しい社会セクターの可能性』(「日本の非営利セクター―その構造と特徴
」) 林雄二郎・連合総合生活開発研究所編 第一書林
- 『日本経済読本(第14版 )』(「日本の金融システム」)金森久雄・香西泰編 東洋経済新報社
- 「The effects of aging on national saving and asset accumulation in
Japan」『The Economic Effects of Aging in the United States and Japan』(The
University of Chicago Press) 以上 山内直人助教授
学会・シンポジウムでの報告等
- 「The Development of Putting-out System in Modern Japan: The Case of
Producing-Center Cotton Weaving Industry」
- 「Small Industrial Firms and Local Productive Systems in Modern Italy」(コメンテーター) 経営史学会
以上 阿部武司教授
- 「人権の国際的比較―北と南」(司会者) 比較憲法学会 伊藤公一教授
- 「Aging and Consumption Inequality」CEPR conference at London他
- 「Labor Demand and Structure of Adjustment Costs in Japan」European
Network on the Japanese Economy 他 以上 大竹文雄助教授
- 「インデックス取引とボラティリティの銘柄間隔差」(コメンテーター) 日本ファイナンス学会 喜井三希代助手
- 「非核兵器地帯をめぐる諸問題」軍縮問題研究会 「A U.S.-Russia Bilateral
Cutoff Treaty」Meeting the Nuclear Challenges of the Next Century
- 「国際平和への日本の取り組み―カナダとの比較を中心に―」新潟大学日加シンポジウム「核実験全面禁止から核廃絶への展望」原水禁国際大会
- 「Security political perspectives on (North) East Asia as a region」Seminar
on Security, Arms Control and Disarmament in East Asia
- 「包括的核実験禁止条約の現状と 今後の課題」核不拡散・核軍縮問題懇談会
- 「核廃絶への道」広島修道大学法 学会 以上 黒澤満教授
- 「A Re-examination of the Effort Effect of Equity in a Courot Oligopoly
」日本経営財務研究学会 「銀行と企業の関係―銀行の株主からみて 」証券 研究会
以上 斎藤達弘助手
- 「An axiomatization of the prekernel of nontransferable utility games
」 International Workshop on Cooperative Games及び ISERセミナー他
- 「The Walras core of an economy and its limit theorem」 The 3rd International
Meetings of Society for Social Choice and Welfare 以上 下村研一助教授
- 「On Pricing for Multimedia」OECD/EC/COMTEC Workshop
- 「地域情報化施策の数量分析」 情報通信学会
- 「Growth and Industrial Transformation of the Japanese Machine Tool
Industry: Further Results」 理論計量経済学会
- 「Evolution of the Technology in the Japanese Machine Tool Industry」
進化経済学会
- 「Technology Transfer and Technology Management in Asian Machine Tool
Industries : Lesson Learned From the Japanese Machine Tool Industry」 East
Asian Economic Association 以上 辻正次教授
- 「The Triangle of biological, social and legal Parenthood in Japan」
国際家族法学会アジア地域会議
- 「高齢者の生活保障と家族法・成年後見法」神戸高齢者生活保障研究会
- 「ドイツ婚姻法について」ドイツ家族法研究会 以上 床谷文雄助教授
- 「債権の集合的譲渡と法例12条―国際私法と実体法の交錯の視点から」 国際私法学会 野村美明教授
- 「経済政策としてのニューディール」日米法学会日本支部第3回総会
- 「Dilemma of Network Extermality, Price Discrimination and Universal
Service」(討論者)
- 「阪神大震災と経済学の課題」(パネリスト) ともに理論計量経済学会
- 「産業復興のための規制緩和国際フォーラム」阪神・淡路経済復興シンポジウム
- 「震災復興と制度転換」(パネリスト) 日本経済政策学会 以上 林敏彦教授
- 「Japanese Direct Foreign Investment : The Role of Technology and Keiretsu」 Conference
on 'Japan in the International Economy and Structural Adjustment in Japan'
- 「Unit Roots and Cointegration Analysis: The impact on Empirical Research
in Economics」
- 「Tariff Policy and Capital Goods Import on Long-run Economic Growth:
Empirical Investigation of Japan's Case」(討論者) ともに理論計量経済学会
- 「The Commercial Paper Market in Japan」 Faculty of Economics seminar
以上 Colin McKenzie助教授
- 「阪神大震災と経済学の課題」(パネリスト) 理論計量経済学会 山内直人助教授
- 「大震災と経済学の課題」「金融危機と制度改革」(パネリスト) 理論計量経済学会
- 「The Japanese Banking System in Future」情報研究基金、ペンシルバニア大学ウオートン・スクール共催コンファレンス 以上 蝋山昌一教授
研究プロローグ 辻正次教授(理論経済学、日本経済論)

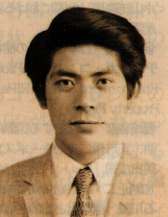
「やはり野に置け、れんげ草、ということでしょうか…」上級国家公務員試験に合格、一時は大蔵省入りも考えたが、結局研究者の道を選んだ心境をこう表現する。
「指導教官から『官僚の世界は本人の努力だけでは不十分。世渡りの術や政治力がないと出世できない』と言われた。それなら在野で研究を続けた方が性格に
合っているかなと思って」京都大学経済学部から大阪大学の大学院へ。
学部生時代から数理経済学に興味を持ち、自分なりに勉強してきたつもりだったが大学院で一級の研究者に触れ自信を喪失。この道を選んだことを後悔した
こともあった。
転機は米国留学だった。阪大社会経済研究所助手になった直後=下写真、日本学術振興会の第1期留学生試験に合格、米スタンフォード大学へ。ここでテーマを絞って一つの研究に没頭、ph.D.を取れたことが自信につながった。
米滞在中の 1973年は外国為替市場が変動相場制に移行した年だったが、その“大事件”の印象が全くないという。それほど専門の研究に没頭した毎日だった
。
現在のOSIPPの学生にも過去の自分を重ね合わせ、研究者としてのプロ意識を求める。「同業者として新しい学際的な学問体系を一緒に作っていきたいと思っているが、研究が質、量とも足りないのでは」。研究生活のあり方を語る時、普段の柔和な表情が一瞬、厳しくなった。
NEWSLETTER TOP
OSIPP HOME PAGE
www-admin@osipp.osaka-u.ac.jp